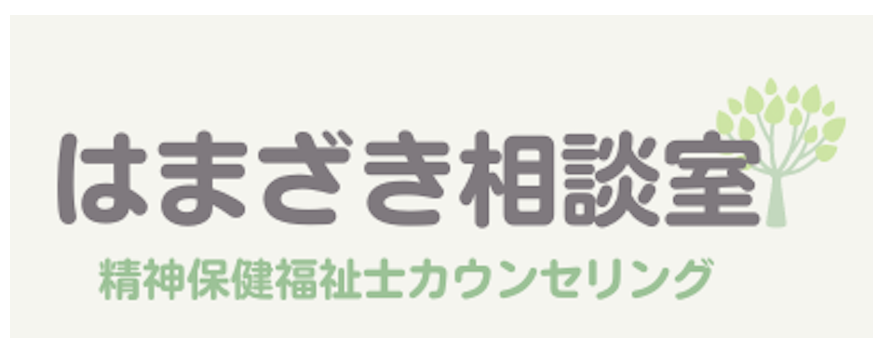依存症とバウンダリー
依存症の人間関係
依存症という病気は周りの人を巻き込みながら進行していく病気だと言われています。
例えば、アルコール依存症の方が酔っ払って寝込んでいるところを家族が布団まで運ぶ、ギャンブル依存症の方がギャンブルで多額の借金を返せなくなると家族が借金を肩代わりする、というようなことを繰り返します。依存症の方はやめたいと思ってもお酒やギャンブルがやめられず、依存を続けていくために家族に嘘をつきます。(飲んでいても飲んでいないと言ったり、家族に隠れて飲酒する、財布を落としたと言って家族からお金をもらうなど)
家族は依存症の方の話は嘘じゃないかと疑う気持ちが大きくなったり、依存症の方の言動を負担に感じるようになり、依存症の方に対して怒りの感情を強く持つようになることもあります。
依存症から起こるトラブルに振り回され疲弊しきったり、この人を立ち直らせるのは私しかいないと思って、考えつくありとあらゆることを試していきます。
依存症は病気だとわかりにくく、困っていても依存症の相談窓口で相談すればいいとは思い浮かばないものです。
病気が進行して、これはおかしいと気づくようになって専門機関で相談し、依存症ですと教えてもらうということはよくあります。
依存症当事者の体験談で、"依存”という生き方しか知らなかったが回復する中で"依存”を手放して新しい生き方を身につけることができた、という内容を伺うことがあります。
ご家族の体験談にも、自分も”共依存”していたことに気付いたという内容があったりします。
人間関係とバウンダリー
私たちは社会の中で生きています。その中でいろいろな人に頼ったり、逆に誰かから頼られたりする。それは当たり前のことですが、依存症をめぐる人間関係の中では一般的な”頼り・頼られる”という関係ではなく、”利用・操作する”という不健康な関係に陥っていきます。
不健康な人間関係になっていると気づいた時に、そこから抜け出すために相手の人との心理的な距離感がどうなっているのか振り返ってみましょう。親しい仲であれば距離感は近いものですが、どれだけ仲の良い家族であっても相手と自分は別の人格を持った人間です。不健康な人間関係では相手と自分の境界線(バウンダリー)が曖昧になっていて、相手の望むことをそのまま受け入れたり、自分の思い通りに相手を動かそうとしたりします。相手の望みをきいてあげられないと自分を責める、相手が思い通りにならないと激しい怒りを感じる、そんな関係から抜け出すには”あなたはあなた、私は私”という当たり前のことを認めることが大切です。自分というものをしっかり持って大切にすること、相手を認めて尊重すること。簡単なことのようですが、意外と難しいと感じるかもしれません。
親しき仲にも礼儀あり、という諺は人間関係での境界線(バウンダリー)の大切さを教えてくれているように思います。
人間関係での境界線(バウンダリー)が無いとか壊れていると感じた時は、カウンセリングを受けたり自分に合った自助グループに参加することが役に立つかもしれません。