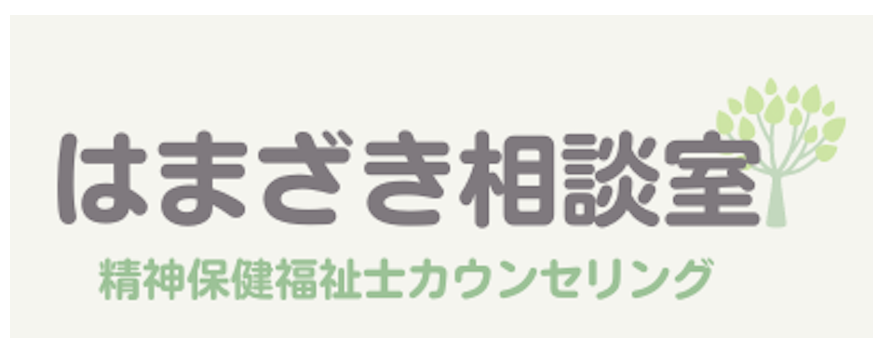マインドフルネスについて
マインドフルネスという言葉を聞かれたことはあるでしょうか。
マインドフルネスは仏教用語のサティ(パーリー語)を英訳した言葉で、サティの日本語訳は「念」「気づき」になっています。日本でマインドフルネスという言葉を使う時には、宗教的な意味合いはなく、『判断や評価することなく、今、この瞬間に意識を向ける』というような意味になります。
マインドフルネスを社員研修に導入している企業があったり、医療分野でマインドフルネスを取り入れられたり、集中力の向上やリラクゼーションの方法として紹介されていたりします。
マインドフルネスについての研究
アメリカでの研究で、マインドフルネスになると脳の血流に変化が見られることがわかっています。マインドフルネスになると、脳の中の扁桃体という部分の血流が減り、前頭葉の血流が増えます。
また、マインドフルネス瞑想を続けることで、脳の灰白質が増えたという研究もあるそうです。
脳についての難しいことは専門家に任せるとして、マインドフルネスが集中力アップにつながるとか、心の安定に効果があるということの科学的な証明になるのだろうと思います。
マインドフルネスの心理療法への利用
マインドフルネスストレス低減法やマインドフルネス認知療法など、マインドフルネス取り入れた心理療法があります。
私の学んでいるハコミセラピーでは、セラピストが手助けしながらマインドフルネスになって自己探索をしていきます。そうすることでいろいろな気づきを得たり、癒し体験につながることもあります。その体験が自己成長につながっていきます。
マインドフルネスは批判することなく、今この瞬間に意識を向けるということですので、自分を客観的に見る力が養われます。
マインドフルネスの日常生活への利用
マインドフルネスになる練習を積み重ねると、日常生活の中でのちょっとした瞬間に「あ、緊張して肩に力が入っているな」とか「鳥のさえずりが心地良いな」とか気づくことが増えます。緊張して肩に力が入ることで体の動きがぎこちなくなっていたら、「深呼吸して落ち着こう」とすることができます。鳥のさえずりが心地良いと感じたら、心地良い感じを積極的に味わうことができます。
何かを集中してやっていて、うまくいかなくて行き詰まりを感じた時に、「一体何が起きているのかな?」と一歩引いて物事を見やすくなったりもします。
いい意味で物事に動じる頻度が減ります。
マインドフルネスが難しいと感じる人もいる
マインドフルネスは今この瞬間に気づくというもので、特別な道具も必要ないですし、そのための場所や時間も必要ありません。
意識の向け方で簡単にできるものではありますが、慣れないと違和感を感じたり、辛さを感じる方もおられます。
自分の体の感覚や内面の感情に触れることが難しいと感じる時は、無理にマインドフルネスになることはありません。そんな時はゆっくりと周りを見回してみて、目が止まるものを少し眺めてみる、ということから試してみるのも一方法です。
自分に対しての優しさと好奇心を持ってマインドフルネスを試してみるのがお勧めです。