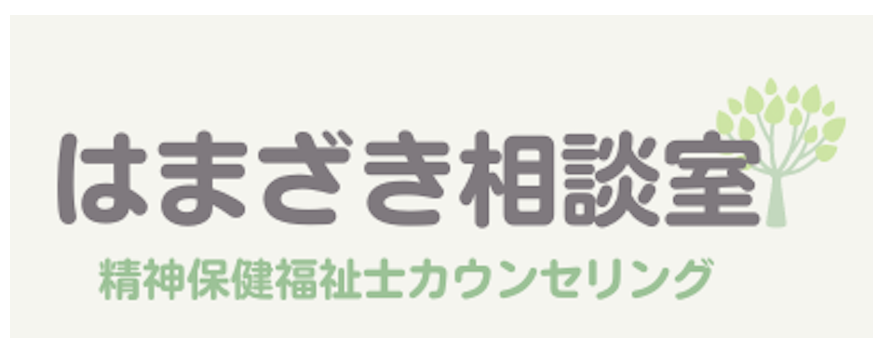自立支援医療(精神通院医療)について
精神的な病気で通院治療を受けるようになった時の医療費について、医療費を軽減する制度があります。それが自立支援医療(精神通院医療)という制度です。
制度の概要
自立支援医療制度には「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の3つがあります。それぞれの医療については対象になる人が違います。
「精神通院医療」は精神的な病気のために通院治療をしている人向けの制度、「更生医療」は身体障害者向けの医療、「更生医療」は障害児向けの医療になります。
それぞれ対象になる治療は細かく決められていますが、ここでは「精神通院医療」について解説していきます。
自立支援医療(精神通院医療)の中身は
精神通院医療という制度を利用すると、どんな医療費の軽減があるのでしょうか。
普通は病院やクリニックで治療を受けると保険診療には3割の自己負担がありますが、この制度を利用すると自己負担が1割になります。つまり医療費が3分の1になるわけです。
さらに細かい規定がありますが、1ヶ月の自己負担額に上限が設けられていて、それ以上の自己負担額は払わなくてもよくなることが多いです。
精神科や心療内科への通院は2週間や1ヶ月に1回は通院して、それも何ヶ月、何年も通院し続けることはよくあります。
風邪ひきや腹痛で1、2回通院したら終わりという病気とは違って、精神的な病気は治るまでに長くかかったり、高血圧治療のように定期的に通院し続ける必要があったりします。治療を続けるために医療費が軽減されるのはありがたいですね。
精神通院医療でカバーできる治療とは
精神通院医療という名前のとおり、通院治療が対象になります。入院治療は精神的な病気の治療であっても対象外です。
通院した時の診察、検査(精神的な病気の治療のためのもの)、薬の費用だけでなく、デイケアや訪問看護も対象になります。
先生の診察と薬だけならそれほど費用がかからないという人でも、血液検査や心理検査をすると費用が跳ね上がったり、復職に向けてのリワークプログラム(デイケア)を受けようとすると3割負担では高くて支払いが辛いということはあるかと思います。
この制度を利用していれば医療費の自己負担が軽くなりますので、治療が受けやすくなります。
ただし治療は精神的な病気の治療に限定されるので、例えば「腰が痛いから、ついでに湿布薬も出してもらえませんか」と先生にお願いして湿布薬の処方をしてもらったとしても、腰痛は精神的な病気ではないと判断されるので湿布薬の薬代は3割の自己負担になったりします。
自立支援医療(精神通院医療費)の利用申請について
この制度を利用するためにはいくつかの条件があります。
①健康保険に加入していること
何らかの事情で無保険になっている場合には申請ができません。(例外として、生活保護を受給している方は保険に加入していなくても申請できます。)
②通院している医療機関がこの制度の指定医療機関になっていること
この制度は指定医療機関でしか利用できません。通院先が指定を受けているかどうか確かめましょう。また、通院先は一つの医療機関だけです。(例外的に複数の病気があって、それぞれ違う病院での治療を受けている場合には二ヶ所の通院を認められる場合があります。)
③主治医に自立支援医療用の診断書を書いてもらえること
申請のためには診断書が必要です。医師によっては医療費が軽減されることが病気を治そうという気持ちにマイナスに働くから、あえて利用しない方がいいと判断されて診断書は書けないと言われることがあります。
また、診断名によっては自立支援医療用の診断書を書ける要件(精神保健指定である、または精神医療について3年以上の診療経験がある)が先生の側にない場合がまれにあります。
上記の条件をクリアできれば、市区町村の窓口で申請をします。市区町村によって受付部署が違うので、事前に問い合わせて必要書類も確認しましょう。
申請書には保険情報、マイナンバー、人によっては年金情報などの記入が必要になりますので、診断書と保険証だけでなくマイナンバーカードがある人は持っていきましょう。
市民税額がわかる書類が必要な場合もありますので、事前問い合わせの時に確認しましょう。
申請するための必要書類は人によって変わることがあります。特に年度途中で引っ越しされた方や、事情があって住民票を他市に置いたままにしておられる方、他市に住んでいる家族の扶養家族になっている方の場合は他市での市民税の証明が必要になる場合があります。このような場合は事前によく確認されるようお勧めします。