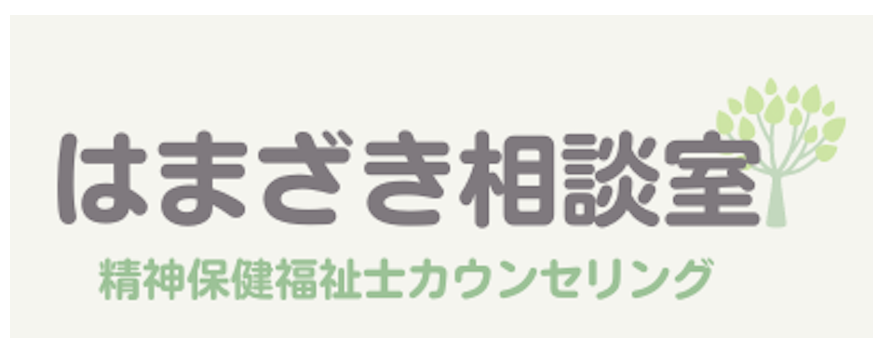障がい福祉サービスについて
障がい福祉サービスは障がい者や難病の方が利用できる福祉サービスで、障害者自立支援法という法律に基づいた制度として作られています。
厚生労働省のホームページには障がい福祉サービスについて解説したページがあります。たくさんのサービスについて書かれていて、制度の全体を勉強するには役に立ちますが、実際に利用したいと思ったとき、どのサービスが自分に合っているのか、利用できるのかが分かりにくいです。
ここでは私が保健センターで働いていた頃、地域で生活している精神障がいの方々がよく利用されていたサービスについて解説していきます。
そのため、全てのサービスについて解説しているわけではありません。ご注意ください。
地域の精神障がい者が利用できる福祉サービス
自宅に来てもらって利用するサービス
居宅介護
自宅に来てもらって利用できるサービスの代表は居宅介護です。
これはヘルパーさんに家に来てもらい、掃除・洗濯・買い物などの家事をしてもらう家事援助と、自分だけではできないところを助けてもらう(例えば入浴介助や食事介助など)身体介護があります。
精神障がいのある方の場合、顔見知りのヘルパーさんと一緒に買い物に行くことで安心して買い物ができ、買い物に自信がついたり、ヘルパーさんと一緒に調理することでお料理を覚えて、一人で料理ができるようになるという方もおられます。
生活訓練(訪問型)
生活訓練は通常は施設に通って利用するタイプの福祉サービスですが、精神障がいのある方の中には、集団に入るのが苦手だったり、通うために公共交通機関を利用するのが苦手だったりする方がおられます。
生活訓練の支援員に自宅訪問してもらい、支援員といろいろな話をしたり、自宅でできる活動をしたりする中で、サポートを受けながら少しずつ生活範囲を広げていくチャレンジをしていきます。
施設に通って利用するサービス
生活訓練
自立訓練という福祉サービスの中に、「機能訓練」と「生活訓練」という種類があるのですが、「機能訓練」は身体障がい者向けのサービスで「生活訓練」は知的障がい者や精神障がい者向けのサービスになります。
人が社会生活を送っていくためには、様々な力を発揮する必要があります。例えば他人とコミュニケーションをする力、規則に則って自分の行動をコントロールする力、適切に体調管理をする力などなど。
生活訓練では自分の病気について学ぶプログラムがあったり、他の通所者と一緒に活動に取り組むことで人間関係の持ち方を練習したり、一人ひとりの課題に応じて参加するプログラムを選びます。
定期的なスタッフとの個人面談で、自分の成長や課題について振り返りの時間を持つことができます。
利用期間は原則2年間になっています。
生活介護
生活介護は日々の生活を豊かに、自分らしく生きることをサポートしてくれるサービスです。
レクレーション的なプログラムを中心にした活動をしているところが多いですが、簡単な作業があったり、施設によっては入浴ができたりします。
利用は障がい程度区分3以上の方(ある程度の障がいの重さがある方)になっています。年齢や状況によっては障がいが少し軽い場合でも利用できることがあります。
65歳になるまでは、利用期間に制限はありません。
就労継続支援A型
障害福祉サービスでありながら、事業所と雇用契約を結んで働くものです。基本的に最低賃金は保障されます。(例外もあるようです)
事業所はハローワークに求人を出していますので、利用するにはハローワークを通しての申込みが必要です。
短時間労働であったり、体調に合わせて出勤日を調整してもらえたり、障がいに対する配慮はありますが、最低賃金保障をするため仕事に対しては一定以上の成果を期待されます。
一般就労の前段階として利用される方が多いようです。
就労継続支援B型
一般的に「作業所」と呼ばれているところの多くは、就労継続支援B型です。
何らかの作業をして、それに対して工賃という形でお金がもらえます。
内職作業のような軽作業をしているところもあれば、喫茶店や食堂、リサイクルショップなどのお店をしているところ、雑貨やアクセサリーの製造販売、クッキーなどのお菓子や餃子などの製造など、作業内容は多岐にわたります。
利用している方の目的も様々で、就労に向けての生活リズムをつけたり集中力を養うためという方おられますし、若い頃は会社で仕事をしていたけど病気のためにしんどくなった、でも仕事はしたいという方もおられます。
利用期間の制限はありません。
就労移行支援
一般就労を目指した訓練をするものです。利用期間は2年以内になっています。
一般的なビジネスマナーを学んだり、パソコンのスキルを身に付けたり、実習として様々な会社で仕事をすることで、自分に合った職種を見つけたり、支援のプログラムは事業所によって違いがあります。
担当者と話し合いながら、自分の向き不向きを確認したり、就職面接の練習をしたりしながら、ハローワークなどで求人情報を見つけて就職に向けてチャレンジしていきます。履歴書や職務経歴書の書き方についてのアドバイスもしてもらえます。
就職した後も半年間は相談にのってもらえますし、障がいをオープンで就職した場合は職場とも情報交換してフォローしてもらえます。半年以降は就労定着支援という別制度を利用することで、フォローしてもらうこともできます。
自分に合った福祉サービスを利用するために
まずどういうサポートが今の自分に必要なのかを相談しましょう。
相談先としては、通院先に相談員がいる場合はその相談員、自分の住んでいる市町村の障がい者向けの相談窓口(相談支援事業所や役所の障がい福祉課など)があります。
障がい福祉サービスを利用するには、市町村の窓口で利用申請をして、利用のための調査を受けます。ヘルパー利用をする場合は主治医の意見書も必要になるので、事前に主治医にヘルパー利用したいと伝えておきましょう。
役所での審査が終われば、障がい福祉サービス受給者証が発行されます。その受給者証で、利用したい障がい福祉サービスの事業所と利用契約を結んで利用することになります。
役所での手続きはわかりにくいところがありますので、相談しながらやっていきましょう。
制度は上手に利用すると、生活の質を上げてくれます。自分の望む生活のため、どんどん使えるものを使っていきましょう。