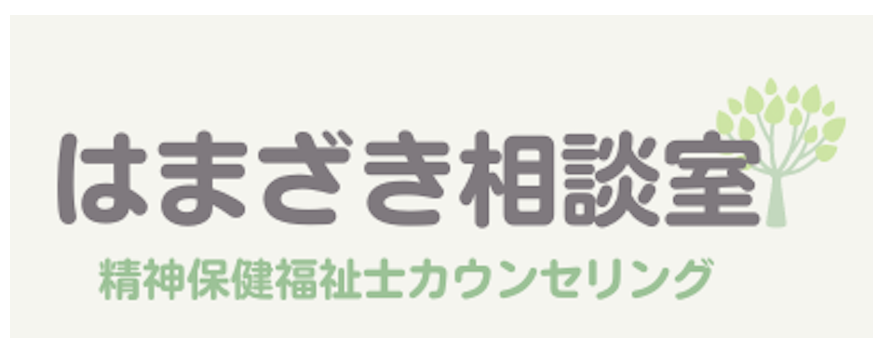成年後見制度について
年をとって認知症になることや、精神障がいや知的障がいのために物事を判断する力が弱い人がいらっしゃいます。
お年寄りが悪徳業者の言いなりになって、必要のない高額商品をいくつも買ったり、必要のないリフォームを契約してしまい、多額のリフォーム代を支払ったというようなことが時々マスコミで取り上げられたりします。
こういう場合に、契約を取り消したりして悪徳業者からお年寄りを守ってくれるのが後見人です。
成年後見制度の3類型
成年後見制度には後見、保佐、補助という3種類があります。
後見というのは、判断能力がとても弱い状態の方のためのものです。後見人は様々な法的な行為をその方に成り代わってします。
保佐というのは、自分の意思はあるけれど、判断をする時に手助けが必要な状態の方のためのものです。保佐人は、あらかじめ決められた法的な行為をその方に成り代わってしたり、ご本人がする時に賛成(同意)したりします。
補助というのは、まあまあ自分で判断できるものの、ここぞという時には一緒に考えてくれたり、何らかの支援が必要な方のためのものです。補助人はあらかじめ決められた法的な行為について、ご本人の代わりにしたり、ご本人がする時に賛成(同意)する事で、ご本人の権利を守ります。
成年後見制度を利用したいですと家庭裁判所に申し立てる時に、後見人をつけて下さいと申し立てるのか、保佐人をつけて下さいと申し立てるのか、補助人をつけて下さいと申し立てるのかを決めます。
どんな人が成年後見制度を利用するのか
私が保健センターで働いていた時に、精神障がいのある方の成年後見制度の申し立てをお手伝いをすることがありました。
ある方は統合失調症で精神科の病院に入院しておられましたが、年をとって認知症にもなってきたので判断能力が低下しました。病院を退院して老人施設に入る時に、入所契約が難しいので後見人をつけたいということでした。
ある方はひとり暮らしをしていましたが、お金の使い方が計画的に出来ず困っていました。また、ご兄弟と共有名義で不動産をお持ちでしたが、その管理もできていない状況でした。
別の方は精神的なご病気に加えて、軽度の知的障がいをお持ちで、その方のお金目当てで近づいてくる男性にお金を巻き上げられ、精神的に調子を崩して入院するといったことを繰り返していました。
このように金銭管理が難しい方や、施設利用などの契約をする時に難しさがある方が成年後見制度を利用されていました。
成年後見制度を利用したら自分では何もできなくなる?
成年後見制度を利用すると、自分では何も決められなくなるのではと心配する方がおられます。
保佐人や補助人をつける場合は、申し立ての段階で、例えば「不動産売買をする時は保佐人に代わりに契約行為をしてもらう」とか、「訴訟沙汰になった時には補助人に相談して同意してもらった上で対応する」とか、してもらいたいことを決めて家庭裁判所からOKをもらいます。ですから、その時に決めなかったことは自分ですることになります。
後見人の場合は幅広く法律行為をその方の代わりにすることができますが、日常生活での買い物までするわけではなく、後見人がついている方でもコンビニでおやつを買ったり、本屋で本を買ったりして日々の生活を楽しまれている方はおられました。
後見人は医療行為(手術の同意など)に関することや婚姻については権限がありません。
この人と結婚します!とご本人が決めたことに、後見人は「その結婚は無効です」とか「婚姻届を取り消します」とは言えません。
誰が後見人(保佐人・補助人)になるのか
親族が後見人になることもありますし、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職の人にお願いする場合もあります。市民後見人といって、専門的な勉強をした上で専門家にサポートしてもらいながら後見人をされる方もおられます。
親族が後見人になるのは、知的障がいを持たれた方の親が後見人になる場合や、認知症の方の子どもが後見人になる場合が多いのではないでしょうか。
親族が後見人になってご本人の資産を勝手に使い込んでしまうということが問題になり、親族が後見人になることが難しくなった時期がありました。ご本人の権利を守るための成年後見制度が権利侵害に使われたわけです。
親族だけでなく、後見人になった弁護士がご本人の資産を勝手に自分のものにして問題になったニュースもありました。
このような権利侵害を防ぐために、家庭裁判所が後見人を監督する人をつける場合もあります。
どこで相談したらいいの?
成年後見制度を利用した方がいいのかどうか、利用したいけど手続きがわからない、などいろいろな相談をしたい時に、どこで相談すればいいのでしょうか。
弁護士会や司法書士会、社会福祉士会といった専門職の会では、成年後見制度についての相談窓口を作って相談にのっています。
高齢者の方には地域包括支援センターで成年後見制度の相談をしています。
市町村で成年後見支援センターといったところを作っている場合があり、成年後見制度についての相談にのっていたりします。
成年後見制度を利用したときの費用について
親族が後見人になった場合は後見人へのお礼といった費用はかかりません。市民後見人に対しても事務的にかかった費用は実費負担しますが、後見人へのお礼は不要です。
専門職の方が後見人になった場合は、後見人が「これだけの後見人としての仕事をしたので、相応の報酬を認めて下さい」と家庭裁判所に書類を出します。家庭裁判所はその内容を審査した上で、報酬をもらっていいですよと決定します。
報酬の額は仕事内容によって違います。家庭裁判所が認めた報酬額をご本人の資産からお支払いすることになります。
資産が少ない方や生活保護受給していて資産がない方でも成年後見制度が利用できるように、専門職団体で報酬分を負担する制度を設けていたり、社会貢献という意味で一定数はボランティアとして受任すると決めている場合があります。
市町村によっては市町村が資産がない方の報酬助成をしている場合もありますので、資産の多い少ないに関わらず、必要な場合は相談してみましょう。